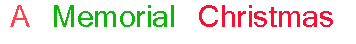
Page 2
ひどく腹が立ったが、表向きは何気なく瞳子の肩を抱いたまま、足早に構内を後にした。
そのまま行きつけの喫茶店に入り、向かい合わせに腰を下ろす。コーヒーを待つ間も、隆裕は不機嫌に押し黙っていた。
「ちょっと驚いちゃった。今日来てるなんて知らなかったな」
「迷惑だったんじゃないか?」
思わずそう答えると、瞳子は軽く首をすくめた。無難な話題に切り替えることにしたようだ。
「卒論、進んでる?」
「……まあね」
「どうしたの? さっきから怖い顔して」
「あいつら、いつもあんなふうなのか?」
ようやく自分の不機嫌の理由を察したらしい。彼女は少し困った顔になり、今置かれたばかりのコーヒーカップに目を落とした。
「やだ、さっきの、見てたの? あんなのいつもの軽い冗談だわ」
「いつもの冗談?」
皮肉な声で唸るように食い下がる。
「へえ、『瞳子サン』はいつもあんなふうに男達とつるんでるってわけか。なるほど、法学部も女が少ないからな。それにあながち冗談とばかりも見えなかったね。どういう意味だよ、あの『例の返事』っての」
「……先輩ったら。もしかして焼いてる? わぁ、自惚れていいのかな、わたし」
普段は名前で呼ぶくせに、こういうときだけ先輩扱いする。さらにムッとした隆裕に、瞳子は少しからかうような、そのくせ何か問いかけるような眼差しを向けた。
この目で見つめられると、俺が何も言えなくなるって、わかっているんだろうか。こういうときの彼女は自分より数段上手だ。とてもかなわない。第一、彼女を問い詰めて、いったい何になる? 瞳子の時間は瞳子のものだ。それを全部縛ることなど、はなからできやしない……。
仕方なく、隆裕は目をそらした。
何だよ、そんなはずないだろ、と言いながら、拳骨をつくって彼女の頭におろすフリをする。
その日はコーヒーだけ飲んで、無理矢理何事もなく別れた。だが、それ以来彼女のことが、さらに気にかかっていた。
自分の知らないところで、知らない奴らの中にいる瞳子……。
まずい。まずいぞ、この思考。ちょっとマジで……。
我に返ると、隆裕は頭を振って意識を原稿用紙に戻そうとした。だが気がつくと、また鳴らない携帯を眺めている。やれやれ。
気分転換にもう一度コーヒーを入れ直そうと立ち上がったとき、背後で軽く部屋のドアを叩く音がした。
彼は三秒フラットでそのドアを開けていた。
◇◆◇
そこにはベージュのショートコートにマフラーを顔半分巻いた彼女が、寒そうに立っていた。
コートの下からは、タイツに包まれた形のいい足と、ふわっとしたダークレッドのスカートのラインがのぞき、手には銀色の大きなラッピングバッグと、しゃれたビーズのバッグを手にしている。
さすがに夜になると外は冷え込む。部屋に流れ込んでくる冷気に気付き、急いで彼女を中に入れてドアを閉めると、小型ヒーターを彼女の方に押しやった。
「寒かっただろ。ほら、そこらへんに座ってて。ごめんな、こんな有様で。今片付けるから」
慌てて机の下に散らばった原稿用紙を拾い上げて、まとめはじめる。
「結構遅かったんだな。先に連絡くれると思ってたけど」
「ご、ごめんなさい、ちょっと混んでて思ったより時間がかかってしまって……。これでも急いで来たんだけど」
そう言いながら、瞳子ははにかむようにマフラーをはずした。その顔を見た途端、隆裕は思わずぽかんと口を開けていた。
彼の好きなあのストレートの長い黒髪が……。よく女達がしているように肩の辺りで短かく切られて、パーマでもかけたのか襟足が軽く流れている。
その上あろうことか……、茶髪になっていた。
彼女は恥ずかしそうにちょっとうつむき加減で、ラッピングバッグを手に立ったままだった。
隆裕は彼女のあごに手をかけ、顔を上げさせた。無言のまま、目を細めてしばらく彼女の顔に見入る。
「……隆裕さん、あの……」
彼のただならぬ気配に気付いたのか、おずおずと言いかける瞳子をさえぎるように、言葉が口をついた。
「なんで、あの髪、こんなことしたんだよ?」
「……え?」
「前の方がゼッタイよかった。お前には似合わない! こんなのは」
言い過ぎたと気付いたときは、もう遅かった。彼女は大きな目を見開いていた。その目に見る見るうちに涙があふれ、頬を濡らし始める。
「そう……。やっぱりね。わたしがバカだった。ごめんなさい、お邪魔しました」
らしくもなく小さな声で言うなり、瞳子は手にした包みをパサリと落とし、鞄をつかむと部屋から出ていってしまった。廊下を駆け去る足音を聞きながら、隆裕はまだあっけにとられていた。何がどうなっているのか、よくわからない。だが彼女が落としていったらラッピングバッグを眺めているうちに、はっと我に返った。
馬鹿はお前だろ! さっさと追いかけないと、取り返しがつかないことになるぞ!
そう気付いた途端、すぐさま部屋を飛び出した。大急ぎで路上に出て左右を探すと、向こうの方にコートのポケットに手を突っ込んでうつむきがちにゆっくりと歩いていく瞳子の後姿が見えた。高いヒールのブーツのせいで、余計に足取りが危なっかしい。短くなった髪のせいで、背中がひどく寒そうに見えた。
気づかれないようにそっと近付いて、背後から両腕を伸ばし彼女を抱きとめた。そのまま胸に引き寄せる。瞬間、彼女が驚いたように身をこわばらせたので、抱き締める腕に力を込めて、安心させるように耳に囁きかけた。
「大丈夫、俺だよ。ごめん、驚かせちゃったみたいだな」
彼女は何も答えなかった。だが、瞬時にへなへなと緊張が解けたのがわかった。胸に心持ちもたれかかってきた彼女の顔に頬を寄せる。その頬が濡れているのを感じ、思わず腕の中で身体をくるりと回し、こちらを向かせた。
街灯に浮かぶ顔には涙の筋が光っていた。
「……ごめん。俺、デリカシーのなさ、最低最悪だ」
彼女はしばらくして、ようやく少し微笑んでくれた。
「……いいの……、もうとっくに知ってるから」
「本当にごめん」
何度も謝りながら涙を指で拭いてやると、瞳子はまた少し笑って手の甲で目元をぬぐった。肩を抱き寄せお互いに寄り添うようにしながら、とりあえず下宿まで歩いて戻ってきた。
「これは何?」
さっき落としていったラッピングバッグを取り上げて、わざとらしく少し振ってみる。
「一応、クリスマスプレゼント。隆裕さんに」
入れたての熱いコーヒーをすすりながら、彼女は答えた。コートを脱いだ彼女はカシミヤの黒いセーターと、ダークレッドのふんわりした柔らかな素材のスカートをはいていた。髪型がいつもとまるきり違うせいか、妙に大人びた雰囲気があった。まるで瞳子じゃないようで、内心少し気がひけている。
「へえ、そりゃ、ありがとう」
そう言いながらかかっているリボンをほどくと、手編みと一目でわかる紺色のセーターと、センスのいい目覚まし時計が入っていた。
「これ、君が?」
照れ隠しに問いかけると、彼女はこっくりうなずいた。
「今時って、言わないでね。編み物は結構好きなの。でもセーターは初めて編んだから、ちょっと不ぞろいでしょ。気持ちだけ、受け取ってくれたらいいから」
「いや、もちろん嬉しいさ。あったかそうだし。それでこっちは? 目覚し?」
「だって……、いつも目覚ましがもう一個あればって、言ってたでしょ? 朝起きられないって」
隆裕は思わず噴き出した。参った、完敗だ。
妙なものを……、と思われたらどうしよう。
男性が欲しいものが、よくわからなかったので、多少緊張していた瞳子は、彼の笑顔を見てほっとしていた。突然隆裕がセーターを脱ぎ始めたのでぎょっとしたが、彼女のセーターに着替えてくれただけだった。
ああ、やっぱり、彼にとてもよく似合う色だ。
努力が多少は報われたかな、そう思ったとき、彼の手がそっと髪に触れた。
「俺個人的にはすごく残念だけど……、別に悪くはないよ、これもさ」
「え?」
「さっきはごめん。君の気持ちも考えないで、ひどいこと言って。もちろん君の好きなようにすればいいんだ。俺がどう思おうが、君の髪だもんな。俺の、じゃないんだし」
さらに驚いたように瞳子は目を見張った。
そんな彼女から、彼は思わず視線をそらした。自分の方が年上なのに、内心こんなに怖がってるなんて、彼女に気付かれたくなかったから。そう、俺は怖がってるんだな……。苦笑して、彼は言葉を続けた。
「なんだか……。瞳子が俺の知らないところで、どんどん変わっていってしまいそうで、怖かったんだ。卒論書きながら、ずっと考えてた。俺達この先も続けていけるんだろうか、そのうち、もしかしたら君が俺の手の中からすり抜けてしまうんじゃないか、なんてね。来年東京に行ったら、今よりもっと会いにくくなるし……、学内は何しろ男ばっかだしさ」
「……ごめんなさい」
ふいに、瞳子はからになったカップをソーサーに置いてポツリとそう呟いた。隆裕の表情が物問いたげになる。
「そんなふうに思ってくれてるって、もしわかってたら、無理してわざわざ髪形変えなかったのに……。本当、馬鹿だな、わたし」
「無理してって?」
「だって、わたしの方こそ……、ずっと怖かったんだもの。隆裕さん、春から東京だし、東京の会社なんかに行ったらもっと大人で、素敵な女の人いっぱいいるでしょ。わたしみたいな子供、きっともう相手にしてもらえないんじゃないかと思って……。だからわたしも、もっと大人っぽくならなくっちゃって、すごくあせって……」
彼女は唇を噛んでうつむいた。
「やれやれ」 ほっとしたはずみに、つい声が大きくなった。
「そんなわけないだろ。なんでそんなこと考えたんだよ?」
「だって、隆裕さん、あの日からなかなか会ってもくれなくなったし」
「だから、それは卒論で忙しかったんだって」
「うん、今はそれもわかったけど……」
机の散らかり具合をちらっと見て、恥ずかしそうに答える。
「信じてなかったわけ?」
「う、ううん、そうでもないけど。あの、それに……」
さらに言いにくそうに口ごもる瞳子を、彼は無言で促した。
「と、友達の話とか聞いてると、何だかみんな、その……、結構すごそうだし。きっとあなたをがっかりさせちゃったんだろうなって、だんだんとすごく心配になってきて……」
「何が?」
訳がわからず眉をひそめる彼に、瞳子はまるで泣きそうな顔になった。
「だから、きっとわたしすごく……、その……」ようやく言いかけ、またためらうように、口ごもる。「へ、へただったでしょ、この前のよ、夜……」
隆裕は今度こそ呆然とした。言葉もなく、ただ彼女をまじまじと見つめ返す。
「わたし……、あんまりにも、そっちのこと経験なさ過ぎで、どうしたらいいとか、全然わからなかったし……、もう、あなたに飽きられちゃったんじゃないかって……思って、わたし……」
次の瞬間、身を乗り出した彼に腕を掴まれ、気がつくと瞳子は彼の腕の中に力いっぱい抱き締められていた。
「馬鹿! 馬鹿だな、本当に」
彼のあやすような低い声が、震えていた瞳子の心をほぐすように、暖かく染みとおってくる。
「まったく……。そんなところも、たまらないよ」
彼がとても優しく見下ろしている。おずおずと目を上げた途端、彼の唇が重なっていた。最初は優しくなぞるようにさ迷っていたキスは、次第に深まり、やがて息もできないくらい激しくなった。
ようやく唇を離したとき、まだ彼女を抱き締めたまま、隆裕はにやっと笑ってみせた。
「さて、それじゃまず食事に行こう。それからシャンパンとかオードブルでも買ってさ。今夜は帰らなくていいんだろ? この前みたいにゴージャスには行かないけど、俺の気持ちだけは、一晩でたっぷり立証できると思うから」
「……もう十分だわ……」
息を大きく吸い込みながら、思わず瞳子はそう呟いていた。いきなりおかしそうに笑い出した隆裕の声が響いてくる。思わずまた、甘えるように彼の胸に顔をうずめてしまった。
彼のこの笑顔があれば、他に何もいらない。 今は心から、そう思えるから。
今夜は、最高のクリスマスの夜になりそうな予感がした……。
〜 FIN 〜





----------------------------------------------------
04/12/24 更新
(あとがき & 新年の更新計画等は、BLOGにて……)