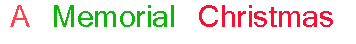
Page 1
11月28日 早朝
素肌にあたるシーツが、とても滑らかで心地いい……。
初めて男の人の腕の中で目を覚ます、ということは、なんだか不思議な体験だった。
触れ合う素肌の感触も、確かに自分の肌とはとても違うのに、なぜか無性に暖かくて、安らぎがあって……。
いつまでも漂いながら、まどろんでいたいような気さえする。
体の痛みは、もう薄らいでいた。
瞳子は指先でそっと、少し腫れてふっくらしている唇に触れてみた。昨夜の情熱の名残が、まだ残っている。
隆裕は、眠りに落ちようとする彼女を腕の中に引き寄せたときと同じように、彼女の肩に片腕を回したまま、穏やかで力強い寝息を立てていた。
彼女がそっと身動きした途端、眠りながらもさらに彼女を自分のそばに引き寄せようとするように、もう片方の腕が体に絡みついてくる。
瞳子はベッドから出るのをあきらめ、夜明けの光の中で、はじめて見る隆裕の寝顔を心置きなく眺めることにした。
昨夜の彼は怖いくらい真剣だった。でも、そのくせ、精いっぱい抑えてくれていたと思う。
自分へのいたわりも気遣いも、彼の動きの全てから、ひしひしと伝わってきたから。
そして、全身を震わせながら思わず叫び声を上げていた最後のその瞬間まで、彼は本当に優しかった。
彼にもらったあの素晴らしい時間を、きっとわたしは一生忘れない。
そして、今も首筋にあたる小さなジュエリーの、硬くて冷たい感触……。
夕べ、ゆっくり食事をとったあと、初めて一緒にこのホテルの部屋に入った。
緊張のあまりひどくぎこちなかったわたしに、二十歳の誕生日のお祝い、と言いながら、彼が手渡してくれた細長い箱。
お礼を口ごもりながら、開いてみてびっくりした。
それはまるで、ドラマの中のワンシーンのようだった。不器用な彼が少しもたつきながら、箱の中から繊細な鎖を取り上げ、そっと首にかけてくれる。
ジュエリーの硬質な煌きを部屋の大きな鏡に映した途端、二度びっくりした。
とっさに言葉も出なくて、ただ問いかけるように鏡に映る彼を見つめてしまった。
その表情が少しからかっているような、冗談めかしたにやにや顔ならよかったのに。そう、いつもの彼のように。
鏡の中でじっと見つめられているうちに、なぜか頬がカッとほてってきた。これは受け取れない。とっさにそう思った。そう言おうと振り返った。
その瞬間、彼の顔が目の前に覆いかぶさってきた。
瞳子は思わずぎゅっと目を閉じた。まるで子供をあやすような低い声が、夢の中のように耳に囁いているのを感じながら……。
大好きな人と共にある時間……。
まるで芳醇なワインのような、贅沢すぎるこんなひと時を、これから先、わたし達はどれくらい持つことができるんだろう……。
宮島瞳子、満二十歳と一日目の夜明け。
ホテルの窓から、不透明な冬の曇り空が見えた。まるで、自分と隆裕との見えない未来を暗示している、そんな空模様……。
ふっと小さな吐息をつくと、彼女は隆裕の腕の中でもう一度目を閉じた。
◇◆◇
12月24日
クリスマスイブにしては、暖かな冬の日だった。
駅前のショッピングモールはクリスマスモード最高潮。冬休みに入り人気の少なくなった大学構内は、一人歩きが嫌になるほどカップルばかりが目に付いた。
工藤隆裕は一人さっき図書館から借りてきた本を手に、下宿の机に向かっていた。机の上にも下にも、週明けに最終提出期限の迫った卒論用の原稿用紙が散らばっている。今どき手書きかよ、とどんなにぼやいたところで、そう決まっている以上は仕方ない。下書きを入れたPCのモニターを睨みつつ、白いマス目を埋めながら、気がつくと三十秒ごとに、鳴らない携帯を眺めていた。
いったいどうしたっていうんだ、瞳子の奴。自分から連絡するって、あんなに念を押してたくせに……。
思わず心の中で呟く。これでたぶん三十回目くらいだ。かといって、自分からかけるのも、無性にしゃくに触った。それじゃまるで自分の方ばかり、彼女に会いたがっているみたいだ。それが事実かもしれない、と思うと何だか苦しくなって、余計に電話もできなかった。
そもそも、クリスマスイブにまだ卒論残してる間抜けなんて、俺くらいだろう。彼女もあきれているに違いない。しかもこんな馬鹿げた羽目になったのは、甘く見ていた自分のせいだから何も言えない。
約ひと月前の彼女の誕生日に、精いっぱいの自分の気持ちを贈ろうと、頑張ってぎりぎりまでバイトをしていたツケが、こんな形で回ってきてしまった。もっと要領よく片付けるつもりが、熱心な担当教授があれこれご指導くださるせいで、予想以上に進まなかった。どうでもいいところで何度書き直したかしれない。もういい加減、経済用語にはうんざりしていたが、これが仕上がらなければ、就職活動の苦労も全て水の泡になってしまう。
まったく、何が嬉しくてこんなことを……。
だが、無事に卒業できないのは、どう考えてもまずい。
資料のページを乱暴に繰ってはまたモニターをにらみつける。そのPCも、最近非常に心もとなくなりつつあった。小さな唸りを立てるかと思うと、時折前触れもなくブラックアウトする。今時考えられないほどミニマムなハードディスクといい、さっさと何とかした方がいいに決まっているが、今はそんな余裕もまったくない。
おかげで十二月に入ってから、瞳子ともすれ違い状態が続いている……。
この前、瞳子と忘れられない時間を過ごして以来、ちっとも会えなくなってしまった。
それでも、あの夜に関して言えば、自分の苦労は想像以上に報われたといえる。彼女が二十歳になったのを祝って一緒にレストランでちょっとゴージャスに食事して、プレゼントにも、学生としては精いっぱい目いっぱいはりこんだ、小さなハート型のダイヤがついたゴールドのネックレスを贈った。その中に今の彼の思いと、それからある種の意味を込めて。
彼女がその意味に気付いたかどうか、はっきりとはわからなかったが、それが本物だということはわかったらしい。とにかく驚いた顔で、こちらを見返していたから。
気を張って平然と見せてはいたが、いつになく無言で寄り添う彼女の肩は、小さく震えていた。そして彼自身もひどく緊張していた。
そして、夢のような無我夢中の時間……。
全てが終わったとき、瞳子は静かに泣いていた。
腕に抱き寄せて心配そうに問う隆裕に、彼女はただ無言で首を振り、胸に顔を寄せてきた。はじめてぴったり寄り添ったまま朝まで眠った。
彼女の甘い香りとぬくもりは、今もまだ彼の体に残っている。そして彼女を愛しいと思う気持は、彼女の全てを知る前の倍以上に大きく膨らんで、あの日から昼も夜も彼の心を刺し続けてきた。
そんな素晴らしい夢の後には、思い切り厳しい現実が残るのも、また世の常で……。
その翌日から、隆裕は遅れすぎた卒論に目いっぱい本気で取りかからざるを得なくなった。友人達の中には、もうとっくに提出している奴も多かったのに、まだ半分もできていない。
もちろん携帯メールのやり取りとか、電話でたわいもない話をするとか、そういうコンタクトは取っていたが、とにかくさっぱり会う時間がとれなくなってしまった。
来年の春、自分はこの大学を卒業する。就職は東京の大手証券会社に決まっていた。証券マンなど、愛想のない自分には一番向かない職業だ、と思っているのだが、弁論部じこみのアプローチが受けたようで、採用が決まってしまった。親はもちろん大喜びだ。
弁論部はとうの昔に引退し、時間があるときにたまに部室に顔を出すだけになっていた。
瞳子も二年生になると、本気で司法試験に取り組むため、法律専門学校に通い始め、同時に部もやめてしまった。
あの部に入ったのは、あなたに会うためだったのかな、なんて彼女が笑うと、それだけで妙に嬉しくなって、怒ることもできなかった。我ながらなんて単純な性格だろう。
来春から、東京本社で新人研修を一年。
その後はどこの営業所に回されるともわからない。
どちらにしても、瞳子との関係はある意味、転機的な局面を迎えていた。卒業後はよくて週末くらいしか会えなくなるのは間違いない。それさえも彼女の方に、この恋愛を続けてくれる意思があれば、の話だった……。
隆裕は再び不機嫌な顔で、モニターの前に置いた携帯の待ち受け画面を眺めた。まだ連絡がない。もう七時過ぎたぞ。まさか、今日の約束をキャンセルするつもりなんじゃ……。
我知らず、深いため息をついてしまった。極力考えないようにしていたあの日の光景が、また目の前にちらついてくる。
あれは今から十日ほど前……。
◇◆◇
『巣篭もり』などと言われつつ下宿にこもっていた隆裕が、久し振りに午後のキャンパスに顔を出した。
せっかくだから少しでも彼女に会っていこうと、瞳子の授業が終わるまで三十分、学内の喫茶店で資料を読みながら時間をつぶした。彼女の時間割はもう暗記している。驚かせてやろうと、連絡もいれず法学部校舎の一階掲示板の前に立って待っていた。
三講目の授業が終わり、わらわらと出てくる学生に混じって階段を降りてくる瞳子を見つけ、下から声をかけようと手を上げたときだった。
「宮島さん、待ってよ」
彼女に、駆け寄ってくる数人の男達がいた。おそらく二年か三年。同じ法学部の連中。彼は思わず真顔になり、手を下ろして様子を窺っていた。
彼女はくるりと振り返ってそちらを見た。やんわりとがめるような口調で答えるのが聞こえてくる。
「やだな。しつこいのは嫌いって、前から言ってるでしょ。前に返事した通りよ。変わりないわ」
「そんなぁ、瞳子サン、それはつれなすぎる。お愛想に少しでも顔出してくれたらいいのに。美女が来ればコンパの盛り上がりも全然違うぜ。ぐっと盛り上がること請け合いだし」
「そんなのあなた達の都合でしょ。おあいにくさま、その日はもう予定があるの。女の子なら他にもいるじゃないの。わたし一人いなくたって、別に大丈夫でしょ。以上この話はおしまい!」
いや、ビジョはいない、ビジョは……、ともごもご言いかける間抜け面の男が、彼女から軽いけん制の一瞥を向けられる。
一様にがっかりした表情が、男達の顔に広がった。そこへ、その中でもなかなかレベルの高そうな奴が、しつこく食い下がるように彼女の肩に手を置いた。
何の権利あって俺の瞳子に気安く触る! おい! と彼の中で怒りが燃えたが、さらに腹が立ったのは今の自分自身に対して、だった。
こそこそ下から様子を窺っているなんて、いったいどういう了見だ?
だが隆裕が彼らの前に出るより早く、そいつが畳み掛けるようにこう言ったのが聞こえた。
「じゃあさ、とにかくまた連絡するよ。例の返事も聞かせて欲しいしさ」
「………。おんなじよ。何度言っても」
彼女の声のトーンが、わずかに揺れたような気がした。それ以上我慢できなくなって、隆裕はその男達をにらみつけながら、階段を上っていった。
「瞳子」
出た声は自分でも腹が立つほど、穏やかに響いた。
「授業終わったんだろ? 待ってたんだ。一緒に帰ろう」
瞳子が驚いたようにこちらを振り返った。長いストレートの黒髪が、ふわりと揺れる。
見る間に彼女の顔に、混じり気のない微笑が広がった。彼の心を捉えて離さない、とても素直な笑顔……。
途端に心臓がズキンと締め付けられる気がした。二週間ぶり。そんなに長い間彼女の顔を見ないで、よくも我慢できたものだ。こんなに会いたかったなんて、今の今まで自分でも気付かなかった。
最後まで食い下がっていた男に鋭い視線を向けながら、隆裕は彼女の肩をこれ見よがしに抱き寄せ、自分のほうに引き寄せた。
素直に従う彼女を見て、連中もようやくあきらめたようだった。チェッと舌打ちしながら退散していく。
だが引き際、そいつが挑戦的に呟いた一言が、隆裕の胸にぐさりときた。
『いいさ、あいつどうせ四年だろ。あと二,三か月の寿命さ』




----------------------------------------------------
04/12/22 更新