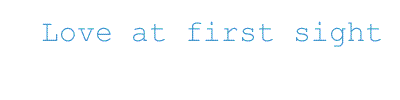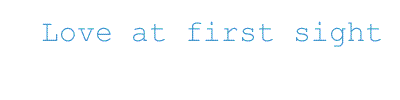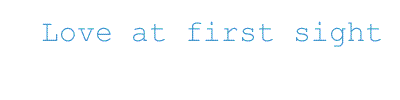 PAGE 2
PAGE 2
「ほら、座ったら」
隆裕は窓のカーテンを閉めると、部屋の隅から座布団を持ってきて、こちらに押し出した。瞳子はゆっくりとその上に座った。目の前で彼が薄手のジャケットを脱ぎだすと、思わず目をそらせてしまう。
「コーヒー飲むかい? それともお茶がいい?」
大きな身体にロゴ入Tシャツと、ジーンズ姿でキッチンに向かい、ガスレンジにやかんをかけている。そのアンバランスさが、なぜか嬉しくて、彼女は微笑みながら立ち上がった。
「コーヒーがいいな。わたしがやりますよ。カップはどこにあるんです?」
「その棚の中……に、客用があったと思うけど」
「あ、はいはい、これですね。あとミルクとお砂糖」
「あ、入れる? 悪いけど今フレッシュ切らしてる」
「じゃあ、いいですよ。なくても」
インスタントコーヒーごときに、何をもたついているんだ。せっかく彼女が来てくれたのに、しっかりしろよ。
隆裕はそう自分に悪態をつきたくなった。マグカップに湯を注ぎながら、大層緊張している自分に驚いていた。今までたとえ女の子と二人きりでいても、こんなふうに感じたことはなかったのに。
「入ったよ」
ぶっきらぼうにそう言って、カップを彼女の前に置いた。瞳子は少し笑っている。まごついてるのがばれたらしい。バツの悪い思いで、隆裕もあぐらをかいて座り、熱いカップを口に運ぶ。焼けるようなブラックコーヒーが、喉を流れていった。瞳子も足をくずし、少し俯いて上品に飲んでいる。それを見ながら、抑えていた気持がだんだんと膨らみはじめるのを感じ、慌てて目をそらすと当たり障りのない話題を探しはじめた。
この人、理絵先輩の彼氏なのに……。いいのかな……、わたし、こんなとこにいても。
少し、落着かない。普段から彼はそれほど口数が多いタイプではない。だが部員のことはちゃんと見ているし、円滑な部活に対する心配りは、行き届いている。隆裕はむしろ不言実行タイプなのだ。だが、部活以外の彼のことは、まだ何も知らなかった。やがて隅にある、就職雑誌を見て何気なく、口を開く。
「先輩、もう考え始めていらっしゃるんですね。就職活動のことも」
「まあ一応はね。まだ、情報収集程度だけど」
「この近くで、ですか?」
「いや……。実は東京に出ようかと思ってる」
え、本当? 思わず嬉しくなって、考える間もなく言葉が飛び出した。
「じゃあ、先輩が卒業されてからも、わたし時々会いにいけますね」
「え?」
「………」
はっと気付いたときは既に遅かった。余計な事を口走ってしまい瞳子は戸惑った。隆裕に射すような鋭い視線を向けられて、顔が赤くなるのが分かる。慌てて、腕時計を見る素振りをした。
「ああ、もうこんなに遅くなってる。コーヒーごちそうさまでした、先輩。わたし、そろそろ……」
「もう少し、いてくれないか」
「え?」
「もう少しさ」
彼の大きな熱い手が手首を掴む。どきりとして顔を上げた。彼を見た途端、その表情に魅入られたように、瞳子は目が離せなくなった。カラカラに乾いた唇を、無意識のうちに舌先で湿す。
その時、隆裕が突然呻き声を上げて、彼女の肩をぐっと引き寄せた。次の瞬間、彼の唇が瞳子の唇に重なっていた。途端にあまりにも甘美な目眩に襲われ、瞳子はくらくらして思わず目を閉じた。隆裕は切羽詰まったように瞳子の唇を開かせると、その中を舌先で探りはじめる。いつしか抱き寄せる手にますます力が加わり、ちゃぶ台は脇に押しのけられ、瞳子は彼の腕の中にきつく抱かれていた。身動きできないほどの力で抱き締めながら、彼の唇と舌は執拗に、彼女の口中を幾度も探り、そのまま頬からこめかみ、そして再び下りて今度は細い首筋へと滑っていく。
彼の唇が熱く首筋から鎖骨を伝いはじめた。大きな手が彼女の腕を愛しげに滑り、やがてスーツのボタンにかかると、瞳子は思わず目を更に固くつぶった。緊張のあまり、心臓がせり出してきそう。彼の腕の中で身体がカチカチに強張ってくる。ついにボタンが外されレースの下着に彼の手がかかったとき、我慢も限界に達した。
「せ、先輩! やめて……」
隆裕が、びくっとしたように顔を上げた。一瞬自分は何をしているのか、というように、呆然と紅潮した彼女の顔を見ていたが、その顔にたちまち暗い陰が宿った。真剣そのものの眼差しの中には、何か表現できない痛みがこもっているような気がした。瞳子の身体を身動きできないほど抱き締めていた腕から、次第に力が抜けていく。
その隙に瞳子は彼の抱擁から逃れるように身をもぎ放し、震える手でスーツのボタンをかけ直した。彼の方を見もしないで、鞄に手を伸ばすと立ち上がった。
「瞳子!」
部屋のドアの取っ手に手をかけた所で、隆裕の押し殺したような声が背中に投げつけられた。ビクッとして一瞬立ち止まったが、もうそのまま振り返りもせずに部屋を飛び出していた。
それから、瞳子は部室に顔を出さなくなった。とても出せなかった。
授業には一応出席していたが、講義はほとんど頭を素通りしていった。携帯に幾度も電話が入ったが、相手が隆裕だとわかると切ってしまった。まだ、いつも通り落ち着いて、笑って話せそうになかったからだ。気持の整理をする時間が欲しい。授業が終わるとまっすぐ自分のアパートに帰るか、気晴らしにクラスの友達とショッピングセンターや喫茶店で時間を潰した。
夜、部屋に一人になると嫌でもあのキスのことを思い出した。彼が好き。そう思うと涙が出てくる。どうしてあんなことをしたの?
単なるはずみか、それとも勢いかな。第一彼は理絵先輩と付合ってるんだもの。理絵先輩もいい人だ。他の女性だったら、彼を取ってしまうなんてことも考えられるかもしれないが、そもそもこういうことに免疫のない瞳子には、とてもそんな根性はない。彼に会ったら無理にでも何もなかったように、振る舞わなければ。
三日目のやや遅い朝、寝過ごして朝食もそこそこに、十時五十分からの二講目に出るため、瞳子はアパートを出た。とたんにいきなり立ち止まる。
そこには険しい表情を浮かべた隆裕が立っていた。瞳子が目に驚きを浮かべて黙って見つめていると、彼はさっと近づいて来て、彼女の肩を掴んだ。
「今から授業? それって、どうしても出ないとまずいのか?」
「……語学だから。あ、でも一回くらいなら大丈夫ですね」
馬鹿正直に答えてしまってから、思わず舌打ちしたくなる。
「じゃあ、別に構わないかな。遅れても。君とどうしても話したいと思って、朝からずっとここで待ってたんだ。あれから何度も電話したけど、取ってもくれなかったし。まあ、仕方ないと思うけど」
大きく息を吸い込んで、彼女の目をじっと見つめる。
「あの晩は……俺……」
何を言われるか分かって、瞳子は彼がそれを口に出すよりも早く、首を横に振った。
「……もう、いいですよ。気にしてませんから。別に大したことじゃなかったわ。わたしあの時のことは全部忘れます。先輩ももう、気にしないで。お互いに忘れるのが一番……」
「大したことじゃなかっただって? 冗談じゃない。それ本気で言ってるのか?」
隆裕は意外そうな、怒ったような声で遮った。彼は瞳子の肩にかけた手にさらに力を入れ、その顔を覗き込む。瞳が傷ついたように、暗くなっていた。
「少なくとも、俺の方はそうじゃなかったんだけどな」
何が言いたいの? 急に動悸が激しくなる。瞳子は目を見張って隆裕を見た。彼の手が震えたような気がした。
「瞳子」
ちょっと間を置いてから彼は息を吸い込み、手を離す。そしてはっきりした口調で切り出した。
「あの晩は君の気持も聞かずに、突然暴走しかけてしまった。悪かったと思ってる。もともと俺の不毛な一方通行だったんだから。だけどあの晩から何をしていても、気がついたら君のことばかり考えてるんだ。もう何も手につかないし、頭にも入ってこない。そろそろ限界だと思った。これ以上じっとしていられなくなったから、はっきりさせたくて思い切って今朝、君に会いに来た」
「……!?」
「こんな話、立ち話もなんだけどさ」
彼はさっと周囲に目を配り、誰もいないのを確かめてから、もう一度瞳子を見つめた。真剣な誠実そのものの眼差しを向けられ、瞳子の心臓がまた痛くなった。
「俺、ずっと君が好きだったんだ。初めて会った時からね」
「で、でも先輩は、理絵先輩と付合ってるんでしょう? みんなが」
「あいつとは同じ執行部の友達同志っていうだけだ。それ以上の関係になったことは一度もないよ。俺は、瞳子に会ってからは本当に瞳子だけなんだ」
目を丸くして彼の言葉を聞きながら、瞳子は最初自分の耳がおかしくなったかと思った。それくらい普段の隆裕からは想像もつかないほど意外なセリフだったのだ。だがだんだんと意味が飲み込めてくると、彼女の顔に喜びと共に茶目っ気のある笑みが戻ってきた。
「それならもっと早く、言ってくれたらよかったのに。弁論部の部長さんにしては、随分弁舌が遅いわ。でもさすが、ポイントついて説得力はあったけど」
くすくす笑う瞳子を見ながら、彼がむっつりと答える。
「こういうのは、あまり経験ないんでね」
「あのですね……」
瞳子はやや上目遣いに彼を見上げた。
「わたしも先輩のことがずっと好きだったんです。それに今はもっと」
気難しい顔で彼女を見ていた隆裕の顔には、まず驚きが、そしてゆっくりと嬉しそうな微笑が浮かんだ。無言のまま、彼女の顔をつくづくと見入っている。瞳子は照れ隠しのように、さっき出てきたアパートを振り返った。
「先輩、せっかくここまで来てくださったんだし、うちへ少し寄っていかれません? まだ来たことないでしょう」
「え、え! いいのか? それに授業は」
「べつにドイツ語なんか、どうだっていいですから。あ、でもいきなりな展開は、もうなしですよ」
「いきなりじゃなきゃ、いいわけ?」隆裕がにやにやしたので、瞳子は怒ってつんとそっぽを向いた。
「そういうこと言うなら、やっぱり学校へ行きますけど」
「……いや、もう言いません」
瞳子は笑った。それに確かに二人とも、授業など受ける気分ではなくなっていた。
「ほら、先輩」
「ねえ瞳子。それならさ、その先輩ってのいい加減で……」
笑いながら元来た方へ引き返す瞳子の後を追いながら、隆裕はぽつりとつぶやく。
参ったな。彼女に頭が上がらなくなりそうだ。
〜〜 fin 〜〜
続編はこちらより → NEXT
TOP / BACK / MENU / HOME
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
04/1/15 更新
初めて書いた日本物で、拙さ全開ですねー!(笑)
お付き合い頂き、どうもありがとうございました♪